筑紫舞聞書(八)
〈聞書(三)で紹介した「うきがみ」伝承の補遺〉
昭和五十八年十二月、私は、光寿斉を、奈良、春日大社の「若宮おん祭」にさそった。
筑紫傀儡子の伝統を受け継ぐ筑紫舞に、傀儡子舞の存在証明ともいうべきいわゆる「」がないわけはない。おん祭の「細男舞」を見たら、何か思い出すのではないか。そんな一縷の望みを抱いて奈良に向かった。
春日大社の花山院親忠宮司(当時)は、心よく迎えて下さり、潔斎に入られるまで、いろいろなお話をして下さった。その中で、
「おん祭一千年の歴史も最初の一日があったればこそですよ。」
というお言葉は、その頃筑紫舞を教えに月に三日、姫路から九州の宮地嶽神社に行っていた光寿斉にとって一番心に染みた言葉であった。
夕方、社務所で、待っていると外の闇から、七度半の使いが、呼び立てに来る。その言い立てを聞いていた光寿斉は、顔色を変え、
「斉太郎さんの言い方とそっくり。」
と言った。山十の店の前でかしこまり、
「大宰府よりのおん使者参りました—。」
と言ったあの調子と全く同じだという。
その頃から、ある予感が、私にはあった。
深夜、若宮の神を迎えたお旅所で、次々と奏上される芸能を、光寿斉は、寒さをこらえてじっと見ていた。
果たして翌朝、宿の奈良ホテルで朝食をとりながら、私が、
「細男舞どうだった。」
と聞くと、
「うん、あんなん、うちにもあるで。うきがみいうんやけど…。」
と言ったのであった。
彼女は、その時、五十年間記憶の隅にとどまっていたうきがみ伝承のすべてをよみがえらせ、矢継早に私に話した。
私は心の中で快哉を叫んだ。また、春日大神のお導きに感謝したことであった。
(以下 聞書(三)「うきがみ」の条に続く)
〈菊村検校の行方〉
さて、また話は、昭和十八年にもどる。
戦争がいよいよ激しくなってきたこの年の夏、検校は、父に、
「長い間、お世話になりましたが、もうお嬢さんに教える芸はなくなりましたので、これでおいとまさせていただきます。」
と挨拶した。側で母があわてて、
「そやけど、戦争もどないなるやしれまへんし、うっとこにおられたら、食べることくらい何とかなりますさかいに、どうぞいつまでなりとおって下さい。」
と言ったが、
「教える芸がないのに、置いていただくわけにはまいりません。」
と言った。何度、引きとめても答えは同じであった。
別れる前に、検校は、光子に盃に酒を注いでくれと言った。光子が酒を注ごうとすると、検校は、
「賜われ、賜われ。」
と言った。光子は、
『あ、九州の時と同じ。』
と思った。今度は、いやがらず、素直に酒を注いだ。検校はそれを飲み干した。
そして、
「いろいろむつかしい事、無理難題を押しつけましたが、私が生涯かけてやった仕事と思っております。くぐつの事、筑紫振りの伝承の道すがら、また、いろいろ申し上げた曲の解釈のことなど、そっくりそのまま持っていて下さらば、いつの日か、何十年、いや何百年先にでも、きっとそのいろいろのなぞを解いて下さる方が現われるでしょう。それまで、伝え伝えて、大事にして下さい。」
と言い残した。
検校とケイさんは、山十の人達に丁重な礼を述べて神戸を去った。
検校が去った翌年の昭和十九年、光子は結婚した。夫は兵隊に取られ、光子は、舞子の別荘にのがれていた。戦火はだんだん本土に近づいていた。
昭和二十年の春、光子の友達が、夫の郷里の長崎へ行っていた時、検校に会った。トミちゃんというその人が、
「山十におってやった検校さんと違いますの。」
と言うと、検校は静かにうなずいた。
「うち、山十の光子はんの友達です。うち、これから神戸に帰りますけど、山十の皆さんお言伝ないですか。」
と言うと、検校は、
「いえ、別に。」
と言う。トミちゃんは、そっけない人やなと思ったが、それでもと、
「光子さんには?」
と言うと、検校は、
「いえ、何もございません。もう、あの人が私ですから…。」
と言ったという。
その年の夏、長崎に原爆が落ちた。
戦争が終わり、昭和二十一年か二十二年のはじめ頃、光子は出産のため、父の郷里の徳島にいた。その時、神戸の実家から手紙が回送されて来た。開けてみると、新聞記事の切り抜きが一枚入っていた。それは、
『通称ケイさんが入水自殺した。』
という小さな記事だった。福岡県あたりの川だったと記憶している。九州から誰かが、神戸の家に身元を隠して知らせてくれたのではないかと光子は思った。
こうして、検校の行方は全くわからないままに四十年が過ぎた。生活が落ち着いてから、光子は、長崎に原爆の落ちた八月九日を、検校の命日と決めてお祀りすることにした。
以上が、私が、河西光子こと西山村光寿斉から、約八年にわたって聞いた筑紫舞に関する話のあらましである。
「あの人が私ですから。」
と言った菊邑検校は、持てるすべてを、一人の少女に与え、自らは、抜けがらとなって神戸を去った。
菊邑検校とは、誰だったのか。本名は、その素性は—。
その後、光子はもちろん、多くの学者達が検校の行方を探した。しかしとして知れなかった。
昭和五十九年、筑紫舞の「翁」に魅せられ、筑紫舞をラジオ番組に仕立てようと、三年がかりで取材していたRKB毎日放送の津川洋二氏が、一人の証人を探し出した。
その人は、福岡県甘木市に住む藤井敬松検校で、当時七十七歳。藤井検校は、この年、當道音楽会の調査で、八橋検校の直系十二世であることがわかり、同会より大検校位を与えられた。
藤井検校の話によると、師匠の松岡検校が明治の中頃、菊邑検校と会ったということであった。以下は、藤井検校が、語った言葉である。
(菊邑検校が)大宰府におられるということを聞いておられたから(松岡検校が)お会いに行ったと言われておりました。
それで、あそこに行かれたらですね。
『松岡さん、こっちに入りなさい。』
と言われて、側に行かれたら、頭からずっと手の先までさすられて、ほいで、
『こんなら良かない。』
と言われて…。
『検校様、御挨拶申し上げます。』
ということで、その頃は厳しかったそうです。
菊邑検校の所に黒田公がおいでになって、
『検校様、福岡城内に歩かれる時は、お忍びで行って下さい。』
と頼みに見えたと。
福岡領から、佐賀の県境まで護衛して、また向うからお迎え に来て、検校の行かれる所に護 衛していかんならん。そういう ことじゃったそうですよ。
(「追跡!消えた放浪芸・筑紫舞の謎」RKB毎日放送制作より)
この話をして下さった二年後、藤井検校は亡くなった。
光寿斉にとってこの藤井検校の言葉は何よりもうれしいことであった。
彼女は私に、
「うちは藤井検校のあの言葉が聞けただけで充分や。」
と言った。
筑紫の地をさすらう一人の傀儡子の芸と、天才箏曲家菊邑検校との出会いは、おそらく近世初頭の浄瑠璃芝居が生み出された時と同じような、芸能の一大飛躍となって筑紫舞を大成したに違いない。
その芸が、偶然とはいえ、検校がこの人こそと見込んだ一人の少女に伝えられた。
その少女は、五十年後、肉親との縁を切ってまで、筑紫へ行きたい、筑紫へ行かねばと思いつめ、遂に、「九州の子」になってしまったのである。
それは、まさしく、傀儡子にあやつられ魂を吹きこまれた一個の人形のようであった。
そこに私は、傀儡子達の芸に対する執念といったものを感ぜずにはいられないのである。
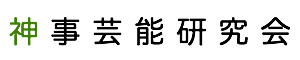
 聞書
聞書