筑紫舞聞書(三)
筑紫舞では、「雲井十年、ふき三年、オキナは生涯」と言う。オキナはそれだけ、大切な舞である。しかもこれは、大曲ではあるが、神舞ではなく、くぐつ舞なのである。命がけの祓えの舞である。
「オキナ」を教えてもらった人は、すぐ誰か次の世代の人に伝えておかなければならない。伝えられた人は、何十年か先にでも、舞えといわれれば、いつでも舞えるようにしておかなければならないという。
七人立ちのオキナの名告りの心得と名告りの言葉などを記す。
◦肥後のオキナ‐袖を外にかえし、右手は扇を胸に抱き、四角い鉄のようにどっしりと、御礼言上の総大将のように「われは肥後のオキナ」。名告りの後、をトンと踏む。
◦加賀(?)のオキナ‐さわやかに、ろうろうと、翁かぶりをして、右手は扇を胸に抱いて「カンガのオキナ」。このオキナは背の高い人がつとめる。加賀と字を当ててよいかわからない。
◦都のオキナ‐扇を半開きにして両手で笏のように持ち、左、右と見ながら、「都のオキナ」。性別なし。水のような透明感をもって名告る。
◦より上がりしオキナ‐扇を閉めて右手に持ち、ひしゃくのように水をすくいあげるようにしながら、腰をかがめて海から上がってくるように「われは難波津より上がりしオキナ。」名告りの後、反閇をトンと踏む。海から上り、野こえ山こえ、息はづませて、遠路はるばるかけつけたような感じで名告る。
◦出雲のオキナ‐扇を開いて、右肩にかつぎ、おもねって、機嫌をとるように「われは出雲のオ ー キナにておじゃる。」名告りの後、ペコッとおじぎ。
◦尾張のオキナ‐扇閉めて、淡々と「われこそは」でトンと右足踏み、左足あげ、扇左肩にやり、くるりと一回転して「尾張のオキナ」。
◦の地より参りしオキナ‐扇を閉めて杖のようにしてショコショコと鳥飛びで出て、軽々しく余り重みをもたせず、左右をキョロキョロ見ながら「夷の地より参りしオキナ」。名告りの後、おじぎ、反閇をトンと踏む。
「都のオキナ」については、その他のオキナがみな固有の国の名を負うているのになぜ「都」と漠然とした名であるかということを光子が聞いた時、検校は、
「その時々の都です。」と答えたという。またこのオキナだけは、「性別なし」であるが、このことについては、光子は検校に質問しなかったので何も聞いていない。検校の教え方は、光子が疑問に思ったことにのみ答えるというやり方だった。
この「性別なし」については、光寿斉氏自身の考え方として、「都には天皇がおられるが、都のオキナは天皇陛下やないやろか、天皇様は、女帝もおられるからやろか。」と私に言われたのが当たっているように思われる。
「出雲のオキナ」については、光子は検校に質問している。扇を肩にかつぐのは袋をかついでいるのだという検校の説明に、光子は、「袋には何が入っているん?」と聞いた。検校は、「着がえの装束が入っています。」と答えたという。光子が「その人だけが、着替えを持って来たん?」と言うと、検校は、「そうね。遠いからね。」と答えたという。
さらに、光子が、「出雲のオキナは、オオクニヌシ?」と聞くと、検校はきっぱりと「違う」と答えたという。検校は誰かは言わなかった。
出雲のオキナだけが、おもねり、へつらって名告りをする。今、私は、このオキナは、大国主神に媚びつきて三年に至るまで復命しなかったと古事記に記すかののことではなかろうかとも考えている。
さらに、光寿斉氏が、宮地嶽大塚の石室において見た「十三人立」については、光寿斉氏の記憶にあるオキナの名前だけを記しておく。この舞は、「宰領さんをおなぐさめするための舞」と言っていて、検校は光子には教えなかった。
◦タカクラのオキナ(あるいはアサクラのオキナ)このオキナが中心に坐っていた。
◦オトという女役が出て、この中心のオキナにしなだれかかったり、口づけをしたり、色っぽい仕草をしているうちに、中心のオキナが立って舞い出したという。
◦七人立のオキナの七人。
◦吉備のオキナ(後述)。
◦オオエのオキナ‐皆の中で一番若い人がつとめていた。一番最後に名乗った。両手を胸で交差させて出てきて名乗った。この人が、光子に大江山の酒呑童子の伝承を語ってくれた。
◦サカニホのオキナ‐小さな人だった。二メーター位跳躍した。あとで、くぐつの一人が、この役の人はいつも変わらない。飛びが得意と言っていた。「酒勾」と書く。
◦機織りの
オトを除くと十二人であり、もう一人のオキナの名前を光寿斉氏は当初は思い出せなかった。しかし数年の後、ついに最後のオキナの名が、光寿斉氏の口をついて出た。それは、「熊野のオキナ」であった。
私は、心の中で『ああ、やはり』と思った。「出雲」があり、「肥後」があり、「難波津」「加賀」「都」「尾張」「夷」「吉備」と出れば、残るは「熊野」しかないと思っていたが、採訪者として誘導尋問してはいけないと思っていたのでひかえていた。
それにしても、十三人の内、十二人まで思い出してその後が長かった。というのは、光寿斉氏が、かつてオキナを教えた時、「肥後」中心のオキナを教えてしまったので、つい、もうひとつの構成である、「熊野のオキナ」中心のオキナを忘れてしまっていたのであった。
「熊野のオキナ」は、伊勢神宮で奉納するとき真になる。伊勢では、
・三人立‐「熊野のオキナ」(真)、「大江のオキナ」、「難波津より上りしオキナ」
・五人立‐「熊野のオキナ」(真)、「都のオキナ」、「加賀のオキナ」、「難波津より上りしオキナ」、「尾張のオキナ」という構成で、出雲のオキナが入らない。検校は、この構成の方が先に出来たが、その後伊勢に奉納することが少なくなり、出雲に行くことが多くなって、「出雲のオキナ」が入った。と言ったという。
「熊野のオキナ」の名告りは、「われこそは、熊野のオキナ(トン・トンと反閇)」
である。野太い声だったという。
「熊野のオキナ」中心の三人立、五人立については、光寿斉氏は、伝承しておられる。
伊勢で舞う時、「熊野のオキナ」が中心となり、「出雲のオキナ」は舞わないが、傍職としてひかえているのである。そして「熊野のオキナ」が名告りをする時、そのうしろに蹲踞の姿勢で隠れている。「熊野のオキナ」が名告ると、うしろからひょいと顔を出して「い、づ、も、の」と切って言い、また、「熊野のオキナ」のうしろに顔をかくし「オキナ」と言って、蹲踞で、ス……と退出する。
伊勢における「出雲のオキナ」の役割はこれだけである。
しかし、出雲で舞う時は、「出雲のオキナ」が真となり、「肥後のオキナ」「都のオキナ」という構成になる。名告り方も、「われは、出雲のオキナなり。」と言う。
ちなみに、尾張で舞う時は、「尾張のオキナ」が真で「出雲のオキナ」「加賀のオキナ」という構成となる。
「三人立ちのオキナ」があがった時、検校が斉太郎と話しているのを光子は側で聞いていた。「これで、一応終った。」と検校。その時、斉太郎が、「おやかたさま、うきがみは?」と聞いた。検校は、「……しかし、あれは、舞うことがないから……。」と言ったが、斉太郎は、「ぜひ、あれを、とうさんに……。」と何度もたのんでいる。しばらく検校は考え込んでいたが、「では、移しかえておこう。」と言った。それに続けて、「しかし、うきがみをやるには、源流をやってからでなければ……。」と言った。
光子は、『また、オキナやろか……?』と思った。七年間、オキナばかりに明け暮れた光子は、正直のところ、オキナにはもう、うんざりだったのである。
検校の言った源流とは、やはりオキナで、「源流おぎな」という一人立ちのオキナで、これは「都のオキナ」である。検校は、
「源流が覚えられんようでは、うきがみはとうてい無理。」と言った。
またこの舞は、一生に一回だけ、しかも五十を過ぎなければ舞ってはならないという舞である。
昭和五十八年、東京の國學院大學の講堂で西山村光寿斉として光子ははじめて「源流おぎな」を舞った。彼女は六十二歳であった。
筑紫舞にはほかにも、以下に述べるように、さまざまな「翁」がある。「赤鬼」という舞が吉備のオキナの舞である。「赤鬼」は、オキナを教えるついでに率先して教えてくれた。「赤鬼」の装束は、翁冠、覆面、白装束(下は赤小袖)を肩ぬきで舞う。覆面の布を首の後ろでねじって左右に棒のように突き出す。これは強さをあらわすためであると習った。
覆面をして舞う舞がいくつかあるが、これは神に対してけがれた息を吐きかけないためである。これをつけて舞った時、息苦しかったが、検校は「苦しみの極限にまで来なければ、神は出ません。」と言ったという。
ある時、この舞(「赤鬼」)を、美作(津山と林野の間位)の神社で舞って欲しいと申し出てきたが、検校は、「お宿りになりますまい。お断わりして下さい。」と言ったという。また、父十三が、笠岡(岡山県西部)の知り合いから頼まれたか何かで、「赤鬼を、笠岡で舞うたれや。」と光子に言った時、検校に聞くと、「神の方角が違います。吉備の神の逆鱗に触れるでしょう。」と言ってやめさせたという。
箏曲で、「の松」という舞が、筑紫舞では「海走りのオキナ」というオキナ舞である。「オノエ」という発音も、筑紫舞では「おのうえ」と言い「老の上」即ち、神のことだと検校は教えた。
この舞は、「りのオキナ」が、海から上がってきて清き渚で、御代の万歳を寿ぐというもので、水けり、波かぶり、砂かぶり、かじ指しなど、海辺で舞うことを表す所作が多い。
「尾上の松」は次の三種類である。
◦一人立‐このオキナは「スミノエの翁」である。また、「の」とも言う。海から出るように、だんだんと立ちあがり、「ハフリ、ハフリ」と呼ぶ。すると祝二人が出て控える。この祝は、お世話方で控えているだけである。
舞の途中で、名告りがある。
「スミノエのオキナ、ことほぎに参上。
国盛えなば、民ゆたかなり
海鎮まらば、民ゆたかなり」
と名告り、一回転して飛んで、ゆらっと坐る。これは海上に座すことを表す。退場する時は、右ひざを立てて一歩ずつ進み、だんだん海に沈んでゆく。
◦三人立‐「松のオキナ」「賀のオキナ」とも言う。三人のオキナが出るが、誰が中心というのはなく、三人が同格である。
三人は「筑紫のオキナ」「イキのオキナ」「マツラのオキナ」である。
舞の途中で名告りがある。
「ワレは筑紫のオキナにて候。」「イキのオキナ参上」「マツラのオキナ参候」とそれぞれが名告り、次に三人そろって「海原鎮めのオキナそろうてえー」と口上する。また、三歌の途中で、「海原千里に聞こしめせ」と口上する。
◦‐五人以上で舞う。これは名告りはない。群舞は祝賀の舞である。また箏を入れず、三絃だけで舞うと神舞となる。
群舞には、男だけの舞、女だけの舞、男と女とが舞う舞の三種があり、男女の群舞は「の舞」とか「散らし」とか言って直会の意を持つ。
一人と三人の場合には、冠に麻緒をかける。これは「鳥居内」ということを表す。群舞の場合は、粋をこらしてやってくる。お国ぶりを表すのだという。群舞は、はなやかで、技巧をこらした舞いぶりである。
検校は、このオキナは、「白浜という、神が住んでおられる所があって、その白浜からやって来るオキナです。」とも言った。また、この舞は、松のある浜辺で舞うと言われたので、光子は、神戸では舞子の松が有名なので、とっさに、「舞子?」と聞くと、検校は、「舞子の松は女松です。尾上の松とはちがいます。」と言ったという。
これを舞う前に、浄衣を着た人が祝詞のように、「鳥船に乗りてはばたくが如く、あれせり。」と大声で唱えたという。
筑紫舞のうち、「安芸より東、近江より西」の舞というのがある。「畿内もの」ともいうがその中に「御印いらずの明石越え」という舞がいくつかある。この「尾上の松」もその一つで、昔、明石の浦を越えるには、御印が要ったが、この舞を持っていれば、御印なしで通れるということだそうである。他に「須磨」「明石」などがある。
検校は箏曲家だから、箏・琴の話も光子にした。「尾上の松」は、カンベ系だと検校は言った。光子が、昔、神戸は、カンベだったと学校で習ったので、「神戸のこと?」と聞くと、
「そう思ってもらってよい。ただ、漢字を思い浮かべるなら『頭』。海の神が満足なさる耳が違う。間が違う。カンベ系を弾ける人があるでしょうかねえ‐。」と言ったという。
このほかに「うちうちオキナ」というのがある。別名「よりよりオキナ」「いろいろオキナ」ともいうが、神社の宮司達が集って舞う。名告りは、「……神社の宮守にて候。」というように一人ずつ進み出て言う。
また、「千代の友」という舞も、宮守たちの寄り合いの舞で、これは名告りはないが、それぞれが狩衣の袖の内側に名前を書く。
さらにヤハタ系(筑紫舞では八幡と書いてヤハタと訓む)の舞を伝えているものばかりが集まる「ヤハタの寄り合い」というのもこの一つである。最初に、「おおやしま ヤハタの神々集い来て、奉奏たてまつる」と口上してから、うたいながら次々と舞う。
この「うちうちオキナ」「よりよりオキナ」は、舞いうたう人がいつも真中で、次々と交替して舞ってゆく。
「寄り合い」という言葉については、このヤハタの舞を教えに来た人が、次のように光子に話した。
「『寄り合い』とは、皆が寄って舞を合わせることを言います。まだ人間がいない頃、ヤスカワという所があって、そこが神様達の寄合所でした。これが寄合の最初です。遠い遠い所です。
談山神社は、山で寄り合ったので『談山』というのです。これは人間の寄合所です。」
そのほかに、光子が聞いたオキナの名は、「枯芝のオキナ」と「コノサクヤ」である。
「枯芝のオキナ」は、神に呼ばれて、山から枯れ芝を踏んで飛んで降りてくる。このオキナは常に一人、神から早く来いと呼ばれて出てきた姿を現すため、体を屈折させる所作が多い。
「コノサクヤ」というオキナは、山の神である。しかし、「コノサクヤ」のコは木ではない。サクは咲くではない。ヤは爺であると教えられた。
奉納で、(現、神戸市北区)へ行った時、段々畑を見て、斉太郎だったか誰かが、「ほう、コノサクヤが出る所ですなあ」と言ったという。
筑紫舞は、神舞とくぐつ舞とに大別されるが、菊邑検校は、この違いについて、「神舞は、わが身をいとわねばならぬと思うて舞う翁。くぐつ舞は、人の身をいとうて舞う翁。」と教えたという。
だから、大きく見れば、筑紫舞のすべてが翁舞と考えてよいと思う。
くぐつ達は、神社の祭礼にくぐつ舞を舞うことによって人々の穢れをわが身に受けた。その受けた穢れを、神主のいないような神社でひそかに神舞を舞うことによって神にゆだねて神から魂をもらっていたのではなかったか。光寿斉氏が少女の頃、神舞を奉納させられたのが、ほとんど、神主のいないような神社とか、誰もいない海辺であったことなどを考えると、私にはそう思われるのである。
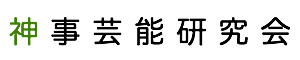
 聞書
聞書