筑紫舞聞書(二)
山本光子(現在の西山村光寿斉)の父十三は、自分でも義太夫を語るほど芸事が好きで、芸人達を庇護した。番頭、女中などの使用人のほかに、家にはいつも何人かの居候がいて、にぎやかだったという。
十三は、家に舞台を作り、一人娘のために師匠を選んでいろいろな芸事を習わせた。山十の家に逗留していた地唄舞の師匠が、前号で述べた通り、九州へ行って菊邑検校を探し出してきた山村ひさ女である。
はじめて神戸に来た盲目の筝曲家菊邑検校は、一遍上人のごとき粗末な僧形であったという。年齢は、五十代半ば、背は高く、堂々とした体躯の人であった。光子は、後に、俳優の山形勲にそっくりだったと回想している。
その検校に影にように付添っていた「ケイさん」は、姓も性別も一切不詳。年齢は三十代半ば。目は見えるが口がきけない。世にも美しい人であったという。後に九州からやってきた伝令(後述)は、この人を「お手ひきさま」と呼んでいた。
ケイさんは、検校とともに山十の家の奥座敷で起居をともにし、検校の身のまわりのこと一切の世話をしていた。
菊邑検校は、いつもは、大変物静かな口数の少ない人だった。検校の笑い顔を光子はついぞ見たことがなかったという。
検校が琴の名手であったということは、鼓膜が二枚あるという耳の良い光子が、生涯あんな良い音色を聞いたことがないと語っているのが何よりの証明となるだろう。
八橋十三曲、賢順十曲といった秘曲を見事に弾じていたという。
しかし、温和な検校も、舞の稽古となるとそれはきびしかった。
目の不自由な検校は、ただ坐って口で指示をし、立って振りをつけるのはケイさんであった。
ある時、光子が、手を挙げるのを横着をして下の方で止めていると、検校が、
「今のところ、ちょっと上へ上げて下さい。」
と言う。目が見えない検校に、どうして判るんだろうと、
「どうして?何でわかるん?」
と聞くと、
「風の切りでわかります。」
という答だった。袖を上げ下げする風の動きで、特に、手を下ろす時に判るということであった。
真夜中に、起こされることも度々であった。ある寒い夜、光子は寝入っていたが、
「すみません、とうさん、今、思い出したことがあるので、来てくれませんか。」
と起こされ、氷の張ったに顔をバリッと突込んで目を覚まして舞台に行った。検校とケイさんは、待ちかまえたように、くり返しくり返し、所作を教え込んだ。
稽古の時は、絹のお腰を着けていたが、夜中に起こされたある時、眠いので、絹のお腰に着替えず、ネルのお腰のままで舞っていると、検校が、
「どうしてそんないじ悪をされるのですか。」
という。どうしていじ悪かと聞くと、絹ずれの音で、所作が判るのだと言った。
検校は、教えたことを決して記録させず、ケンケンや、おじゃみなどの遊びにとりこんで暗記させた。
検校とケイさんは、手とり足とり、むずかしい間を寸分狂わず、必死で光子に教え込んだ。ちょっとした狂いでもあれば、ケイさんがビシッとたたく。やんちゃな光子は、くやしさにケイさんの足をひっかけてけつまずかせたこともあった。
好奇心から習うと言ってしまったが、さすがの光子も、この二人がかりの猛攻撃にしりごみし出した。さりとて、父との約束は絶対であった。それで、日曜日には、朝から一日中映画館へ逃げたりした。そんな時、二人は必死で光子の行方を探し、映画館に呼び出しがかかって連れもどされたこともあった。
検校は、光子の性分を知り抜いていた。いや気がさしたと感じると、
「こんなむずかしいのは、とてもできないでしょうな。」
と言う。すると勝気な光子は、心の中で、猛然と、
『なに、やってやる!』
と思うのであった。
検校は、九州の人というだけで、誰もその住所は知らなかった。ただ、皆は、太宰府辺りに住んでいるのではないだろうかと思っていた。というのは、時々、九州からやって来る伝令がいて、この人は、山十の店の前に来ると、必ずかしこまって大声で、
「太宰府よりのおん使者参りました!」
と呼ばわったからである。
この人は、という名であった。
年齢は四十歳位、手甲、脚袢の旅姿で、きりっとしたよい男であった。
筑紫斉太郎は、検校のことを「おやかたさま」と呼び、店の者が、
「検校はんのお部屋におとりましょか。」
と言うと、
「めっそうもない。わたしら、おやかたさまと枕をともにするのは、おやかたさまのお船入り(亡くなること)のときだけでございます。」
と言って、いつも納屋に床を敷いてもらって寝ていた。
この「太宰府よりのおん使者」という筑紫斉太郎が来ると、間もなく検校は、ケイさんと九州に帰って行き、またしばらくすると神戸にやってくるという生活だった。
光子が女学校二年生になった昭和十一年の秋のこと(十一月十日ごろ)であった。光子は十五歳になっていた。
検校は、光子、父十三、山村ひさ女を九州へさそった。その時検校は、
「本場の舞をお見せしよう。」
と言った。
検校に導かれ、一行は、最初の日は、太宰府近くの二日市温泉に一泊した。翌日、汽車と馬車鉄道を乗り継いである駅で降りた。そして小高い丘に登って行った。その道のほとりに柿の木があって、実が沢山なっている。光子は思わず手をのばして実を取ろうとした。
その時、斉太郎が、
「今日のあなたはそんなことをしてはいけません。」
とたしなめた。
しばらく登って行くと大きな洞窟の前に出た。それは、古代の石室であった。
そこには、いろいろな風体の男達が集っていた。皆、上品な顔立ちであった。男達は、それぞれに持っていた衣装に着がえたが、それは一様にぼろぼろの衣装だった。そして、わらで鉢巻をした。
その丘から海が見えた。男達は海に向かって両手を広げ、大気を吸い込むような仕草をした。
石室の中にはかがり火がたかれていた。中は巨大な石でおおわれていた。中程の両側に長方形のくぼみがあった。
石室の一番奥に検校が坐り、その側にケイさんが坐った。光子と父と、山村ひさ女、筑紫斉太郎、山十の番頭は、中程のくぼみに坐った。
一同の座が決まると、男たちは、次々に石室に入って来た。
そこで、光子は不思議な舞を見た。男たちが舞いながら歌っているその歌詞を聞けば、それはまぎれもなく「翁」であった。舞は二番あり、後にその一つを光子は習った。それは、「七人立ちの翁」というものであった。もう一つは、「十三人立ちの翁」。(これは習わなかった)
「十三人立ち」は、舞人が十三人、この翁舞は、後に光子が習った翁‐一人立(源流おぎな)、三人立ち、五人立ち、七人立ち‐などとは全く違っていた。中心は、タカクラの翁(あるいはアサクラの翁)で、「オト」という女役がいて、その中心の翁にしなだれかかり、色っぽい仕草をした。その女役がしわくちゃの老人だったので、若い光子は、
『いややわぁ、あんなことして、すかんわぁ……』
と思った。
しかし、舞そのものは、寸分の狂いもない見事なものであった。
楽器は、笛、鼓。そして、もう一つ、光子が見たこともない楽器があった。それは、琴板のようなものをわらならをといて茶筅のようにしたもので、たたきつけてシャッシャッという音を出すものであった。
また男たちのはいているわら草履の裏に金属がついていて、それが石室にカチャカチャと反響していた。
不思議なことに、いつもの光子の稽古の時とは違って、検校は琴を弾かず、終始、おし黙って坐っていた。
その舞が終わると、側にいた一人の男が、光子に、用意してあった白むし(あずきの入っていないおこわ)を葉に盛り、舞人一人一人に与えるように言った。(この葉は、後に、おがたまの葉であったことがわかった。)
言われるままに光子は、一人一人進み出る男たちに白むしを与えた。男たちは、それぞれ、「賜われ、賜われ」と言って押しいただき、ふところに入れた。
次に、また、側の男が、かねてから用意の酒をとり出し、男たちに注ぐようにと光子に言った。しかし、光子は、お酒は、芸者さんや女中さんが注ぐものだと思っていたので、
「そんなん、いやや。」
とそっぽを向いた。男達は、それでも「賜われ、賜われ」と進み出て、座が一瞬動揺した。その時、はじめて検校が、ひとこと、
「あせるでない。」
と言ったので、皆は、ひきさがった。
石室を出た時、光子は先程見た「十三人立ちの翁」が妙に心に残ったが、あんな舞を習わされるのはいやだと思って、検校に、
「あんなきちゃない翁、いらんわ。」
と言うと、検校は、
「お前さんの器量なら、七人立ちまででしょうな。」
と言った。
石室からの帰り道、父が、
「あんな舞、お前が五十年かかってもよう舞えんやろな。」
と言った。山村ひさ女は、十三に、
「そやけど、検校はん、うちらを呼んどいて、お琴も弾かれんて、失礼やおまへんか。」
と言った。すると、十三は、
「あれで、ええんや。」
と言ったという。
十三は、男たちに、せめて御祝儀をと、途中の酒屋で酒を買い、番頭に持たせて、石室にやったが、その時は、もう誰一人いなかったという。
あの人達は、誰だったのだろう。ある人は、プンと薬のにおいがしたので、光子はお医者さんかなと思った。ある人は、
「があるので帰らなければ……」と言っていた。父に、
「クジて何?」
と聞くと、
「裁判のことやろな。」
と言った。
『はあん、あの人は、弁護士さんしてはるんやろか。』
と光子は思った。
山伏の格好をした人も一人いた。
また、光子はこんな会話も聞いた。
「去年、舞ったのは、あの山の向こうでしたな。」
‐すると、毎年、この石室で舞っているのではなく、いろいろ違う所で集って舞っていることになる。‐又、こんなことも聞いた。
「おやかたさまの前で舞うのも、これが最後だろう……。」
この時は、検校とケイさんは、光子達と一緒には神戸には帰らなかった。
光子たちが九州からもどり、しばらくして検校はまた神戸に来た。
この時から、検校は、光子に筑紫舞の奥儀ともいうべき「翁」を教えはじめた。「翁」について検校は、次のように語ったという。
「日本四十八州あれば、その四十八州のすべてに翁がいます。翁は、神に近い長老で、おじいさんではありません。」
「オキナは、かなで書いて下さい。できれば片カナで書いて下さい。(以下「オキナ」と記す。)」
また「オキナ」の発音も、「沖のう」というような感じだったと光寿斉氏は言う。
筑紫舞は、圧倒的に海を背景にした舞が多い。海から神が祝福に来て、砂浜で舞うという形をとるものが多い。
オキナも、検校は、
「私達のは、『海のオキナ』です。アマテラスも私達のは『海照らす』です。夜の海に月が映ってきらきら輝いている、これがアマテラスです。」
「海のオキナは、一朝事ある時は、鳥船に乗って空をかけて来ます。誰よりも早く来る。そして千秋万歳をとなえるのです。海のオキナを持っていれば、みんなが大事にしてくれます。」
と語ったという。
また、筑紫舞のオキナが他の「翁」と決定的に違う点は、面をつけないという一条である。 父十三は、翁といえば、面をつけるものと思っていたので『いよいよ翁か』と心はずんで、検校に、
「お面なら、京都で作らしますさかいにな。なんぼ程作らしまっか。」
と聞いたが、検校は、
「故あって、私どものオキナは面をつけません。」
と答え、十三を落胆させている。
検校はまた、
「筑紫舞は、わざおぎの先祖、面をつけずにそのものを演ずるのがわざおぎの伎量です。面をつけて舞うのは、伎楽です。」
「素面神楽は、格が高い。渡来の面は大きい面で、あれは、『おどし』です。『鬼面人をおどろかす』ということです。」
「舞の表情は、神の表情、それにちょっと手をかす意味で、鉢巻など色をかえたりしてつけますが、これは、人間が見分けるためのもの、演ずるものが神になりきれば、そういうものは必要ありません。
面をつけると、吐いた息が戻ってしまうので、祓えになりません。」
面をつけないという一条は、検校は、厳しく光子に言い渡した。
あるくぐつの人が、光子にこんな話をした。
「顔におできができていた人が、すい出しをはって舞ったら、祓串が折れた。その人は平伏してしまい、控えの人が続けて舞ったということがありました。私のもう一人上の人が、『お前はなぜ、自然の薬をつけなかったのか。そこの部分(すい出しをはっていた部分)だけが人間で神になりきれていなかった。』と言ってその人をしかりました。」
面はおろか、人工のものは顔に一切ほどこしてはならないということだとその人は言った。光子が、
「そやかて、女の人は、お化粧しやはるやろ?」
と聞くと、その人は、
「修業ができていないうちは、真白に塗りますが、修業ができてくると化粧が薄くなります。首は塗りません。ほんとうに修業ができてくると、顔と首の境目がなく同じ色になります。」
と言った。
検校に付いていたケイは、化粧も一切しないのに、色が白く、口びるも赤かったという。
筑紫舞のオキナは、別名「いのオキナ」とも言い、それぞれの国の名を負ったオキナが登場し、国名乗りをする。
光子はまず「五人立ちのオキナ」から習った。「五人立ちのオキナ」は、中心が肥後のオキナである。他に、のオキナ、都のオキナ、難波津より上がりしオキナ、出雲のオキナが登場する。
「五人立ち」の次は「七人立ちのオキナ」。「五人立ち」に、尾張のオキナ、えびすのオキナというのが加わる。中心はやはり肥後のオキナである。
次に「三人立ちのオキナ」を習ったが、この間に「りんぜつ」を習った。「三人立ち」は都のオキナが中心で、それに加賀のオキナ、肥後のオキナが登場する。
オキナたちは、それぞれ違った所作をする時もあれば、ぴたっと同じ所作になる時もある。
この複雑な構成をもつオキナ舞の教え方は、おおよそ次のようであった。
最初、それぞれのオキナの所作を通して習い、次に、それが出来ると、まず、肥後のオキナで舞い出して、しばらくすると、
「都!」
と言われる、都のオキナの所作に切り換えて舞っていると、今度は、
「加賀!」
と言われる。すると、すぐに加賀のオキナの所作に切り換える。
このようにして、何度も何度もくり返し、一人の舞手の中に、すべてのオキナをたたきこんでいった。
もう、その頃の光子は、普通の筑紫舞なら、一日に二‐三曲は覚えてしまう所まで来ていた。しかし、オキナは別であった。実に七年という長い年月をかけて検校は、筑紫舞の奥儀を伝授していった。オキナの詞を三行程進み、そこで間に普通の筑紫舞を二‐三曲あげて、又オキナにもどるといった毎日であった。
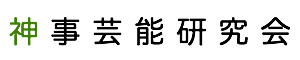
 聞書
聞書