筑紫舞聞書(四)
光子が検校から習っている舞がの芸であることがわかると、光子の母はあわてた。しかし、祖母はると父十三は動じる気配もなく、それどころか、父は神社の御祭礼に酒を奉納しては、娘にこの舞を舞わせた。後に光子はこのように回想している。
「九州から菊邑検校が舞を教えに来るようになって二年目の時、検校より請われるままに灘のほうの神社(神社)で舞ったことがあった。それが『神舞』の一つで、その時から父は、神社で私を舞わせたくて、眼の色変えて『どこかの神社に改修はないか』『何かの記念祭は』とあちこちの神社に奉納させることに生甲斐を見つけたようで、お蔭で私は、神様は舞がお好きと勝手に思い込むようになった。」
祖母はるは、豊岡藩の藩医娘で津田塾の第二回生、ドイツに留学した外科の女医であった。はるは、幼い光子に古典の手ほどきをし、光子は、おじゃみ(お手玉)をするにも、「祇園精舎の鐘の声‐」などと歌って遊んだ。
この祖母も、検校の人格に敬意を表していた。検校は、光子に舞だけではなく、神様や仏様の話を子供にわかるように教えた。検校と光子が稽古の合間に話をしている時、近所の友達が遊びに来ると、祖母は、
「光子は俗世を越える修業をしとるんじゃ。」
といって、会わさなかった。
昭和十三、四年頃の春のことであった。検校と斉太郎が何か話している。どうやら、九州から誰かを呼びたいらしい。検校が、
「が何人か残っていないか。」
と言ったのを光子は聞いた。
何日かして光子が、道で友達と話していると、斉太郎が、お遍路さんのような白装束の三人の女性とこちらへやって来た。斉太郎は光子に、この人達が今、九州から来たので迎えに言ったのだと言った。三人は、九州弁で、
「山十のお嬢さんですか。」
と言ってぺたっと光子の前にひれ伏した。光子は、恥ずかしくて赤い顔をして立っていた。
三人の女達は、とにかく、にぎやかで底抜けに明るかった。何やら言っては大声で笑いあっていた。年は、皆、三十代であった。
その人達が、光子に女の跳躍の所作を教えてくれた。その頃は下ばきはお腰だけであったから、隠し所が見えないように飛ぶにはどうするかなどということを教えてくれた。
その夜、父が、歓迎の席を設けた。その女達は父や山十の番頭達とにぎやかに打ち興じ、
「女じゃというとり物をもてるものより大きい見せて、頂戴ものを沢山いただかな。」
「男はんは全部が男、女は、女というとり物を見せる時と子を産む時。」
などと言ってにぎやかに笑い合った。しかし決して媚びる風情はなく、さわやかだった。誰かが、
「神さんも女の色気をほしがりまっか。」
と言うと、
「神様は男も女も欲しがりません。捧げものの舞とその心が欲しいだけ。」
と答えた。また、歌もうたった。
「神舞で女のとり物振りかざすならば、河原へ行きやれ。ガータロ(河童)が尻子玉抜いて喜ぶじゃろ。」
という歌だった。
三人の女達は、酒が強かった。父が、自慢気に、
「うちの酒は、どないだっか。」
と聞くと、女達は、
「私ら、酒は皆同じでござんす。」
ときっぱり言った。父はおもしろくなさそうだったが、光子は、媚びない人達だなと思った。
光子が母に、
「もう寝なはれ。」
と言われて、席を立とうとした時、それまでだまって坐っていた検校が、女達に、
「退出せよ。」
と言った。光子は、先程から三人のうちの一人が、にぎやかに騒ぎながらも、時々、上座の検校のほうをチラ、チラと見ていたのを見のがさなかった。
女達が立って座が白けそうになったので、母があわてて、
「そやな、今日は、特別やさかいに、もう少し居なはれ。」
と言ったので、光子がまた坐ると、女達も、坐った。
比丘尼組といわれた三人の女達は、翌朝早く、光子がまだ寝ているうちに山十の家を出て行った。
三人は、昨日、松尾さん(京都の松尾大社か?)から和歌山のほうへまわり、和歌山から船で高知へ行って、また船で九州へ帰るのだと言っていた。
斉太郎が言うには、九州には、比丘尼組のほかに女組という人達もいるという。比丘尼組は、呼ばれてあちこちへ出かけて行くが、女組は九州から離れない人達で、普通は「ごないしょはん」と呼ばれている。「ないしょ所」という所にいて「ないしょ頭」一人がとりしきっている。「ないしょ頭」は、四年に一度くじで決める。斉太郎は、
「お月さんと潮の加減で変える。」
と言っていた。
比丘尼組の三人の女達は、さわやかな一陣の風のように光子を吹き過ぎていった。
次の話は、比丘尼組の女が語った「ヲトタチバナ」の話である。この人はもともと千葉の出だが、流れ流れて広島の福山で、琴の塗師(か木地師)と一緒になったと言っていた。
光子はちょうど学校でヤマトタケルの話を習っていた。弟橘媛が身代りに入水する話が心に残って、たまたま来ていたその人に話した。光子が、
「お姫さん、人柱になって殺されて、かわいそうや。」
と言うと、その人は、
「それはね、その姫は、死んだんではないんです。」
と言って、彼らの伝える「ヲトタチバナ」の話をしてくれた。しかし、「ヲトタチバナ」とは言わず、タケルの妃(きさき)とか、ミコの妃とか、姫とかいうように言った。また「ヤマトタケル」とも言わず、ただ、タケルとかミコとか言った。
「姫がタケル様について行って、海が荒れた時、姫は船の舳先に立ち、かくし所—ほと—を見せたんです。そしてくしげを抜いて海に沈めました。すると海の神が鎮まって、ミコは無事に海を渡られました。けれども、姫は、タケル様でない方に、ほとを見せてしまったので、ミコの妃でいられなくなり、ミコとお別れしてその地にとどまり、三年間身を隠し、三年後には、神に変身されました。」
こんな話であった。そしてその人は、
「その舞があるけれど、とうさんには無理ですね…。検校様にしかられます。」
と言った。光子には、その舞を教えると、何故検校にしかられるのか意味が判らなかったが、それは後で、川崎から来た人の話で判った(後述)。
比丘尼組のその女の人は絵巻のようなものを持っていて、光子に見せてくれた。そこには荒れる海が描いてあって、一人の女性が船の舳先に立っていた。そしてその絵の所々に、
「かくし所をあらはにす」
とか、
「海神、これを見そなはす」
とかの短い文字が書かれていた。光子は学校の話とはだいぶ違うなと思ったが、これはまた全く別の話なのだと思おうとした。光子は続けて聞いた。
「その舞はどんな時に舞うん?」
「海が荒れた時、命をかけて舞います。です。この舞は人々のために海を鎮めるという時だけに舞うのです。自分自身の祈願のために舞ってはならないのです。
そのかわり、これを一度舞ったら引退しなければなりません。二度と舞えません。そしてその後、三めぐり(三年間)は神様の前に出られない、うつし身を隠さなければなりません。その間に、次の人にこの舞を伝えなければなりません。私の知っている限りでは私までで三人おりました。皆、伝えては身を隠しました。もう一人おりましたが、その人は、自分の夫が漁に出た時、海が荒れたので、自分の夫のために舞ってしまったので、追放になりました。海は鎮まり、夫は帰って来ましたが、真の性根がわかっていないということで追放になりました。この舞は、一生に一回しかできないんです。
一番最近では、関東大震災の時、津波が来るということで、東の海に向かって舞ったと言うことでした。」
こんな話であった。光子はわけ知り顔でこんなことも聞いた。
「そういうことをするのは、処女の方がいいとちがうん?」
するとその人は、
「男を一人だけ知っている女の方がいいんです。心がわかるから。でも、子供を生んだ女はいけません。そういう人はほとんど子供が出来ないんです。私も子供がおりません。」
と言った。
こんなことがあって、日ならずして、今度は川崎から男の人がやって来た。光子が前の話をすると、その人はそれを補うように、またいろいろな話をしてくれた。この舞はとなえ言葉があって、
「わだつみの わだつみの神 しづまりませ わがほとをささげまつらむ おほきみのため」
という。舞った後、この言葉を言ってから身を隠すのだと言った。光子が、
「お姫さん、ミコトのために死んだのに、『あずまはや』とたった五文字しか言ってもらえないのはかわいそうや。」
と言うと、その人は、
「そうではないんですよ。ほんとうはね、もっと長いんです。
『わだつみの神の怒りを鎮めぱや ほとをささげて消えにし姫を われはしのぶぞ、あづまはや』」
と祝詞のように唱えた。
その人は、舞の所作を少ししてみせてくれたが、それは裾をゆっくりと手で左右に開いて、その裾をゆっくりと頭上にかぶるというものであった。
この舞はかくし所を顕わにし、神に捧げる舞であった。比丘尼組の女が検校にしかられると言ったのは、こういう所作があるからだと光子は納得した。
この舞は「オクンチ(国土)の代身」の舞という。その人はこんな話もした。
「ほとを捧げる舞は、本来は相模海女(さがみあま)が持っている舞である。相模海女は腰が太く、力仕事もよくする。相模海女はほとで稼ぐ。尊い人のお種をいただいて生んだ男子は、皆、英雄豪傑になる。越の海女はほとでかせいではいけない。ほとで稼ぐ—春を売る—のは相模海女にまかせる。」
またこんなことも言った。
「タケルのミコが火攻めに遭われた話は農耕を教えているのです。」
ヤマトタケルにまつわる話は、傀儡子たちの大切な伝承であったらしく、その他にも各地から来た人々によって語られた。
その中で、三重県の亀山から来た人は、「天かける衣」の話をし、「時のタケル様」という言い方をした。
「時のタケル様が亡くなった時、真白な衣がその地の空をおおいました。なきがらは無く、玉と冠と麻緒が残っていました。この方は神であるからなきがらはないんです。トコヨにゆかれたんです。
その衣が空を飛び、その土地の神聖な岩の上にふわりと降りました。これが『天かける衣』です。その岩の辺りが輝いていたので、人々がそこへ行ってみると、その岩の上に一羽の白い大鳥がいました。その大鳥は『私がお役に立ちましょう』と言いたげにそこにおりました。
そこで人々は、その大鳥の足にタケル様が残した麻緒を結びつけて、ミカドに知らせるようにと言いました。『たのむぞ』と言うと、大鳥は一気に空をかけ、一昼夜で飛んで、ミカドに知らせましたが、そこで力尽きて死んでしまいました。そのなきがらをまつった白鳥陵というのもあるんです。
タケル様の亡くなった所(亀山)には、玉と冠と麻緒が納めてあります。タケル様の身代わりの大鳥をまつった御陵と、御陵は二つあります。亀山の方は、私どもが皆でお守りしています。
タケル様が亡くなって魂となった時、ほとを捧げた姫が迎えに来て出会ったということです。」
光子は信じられない気持ちで、
「もし、出会わなかったら、どうなるん?」
と聞いた。その人は、きっぱりと、
「ヨミヘ行きます。ヨミは誰でも行けます。トコヨは魂の触れ合う所、魂の高い人でなければいけません。」
と言った。
この話の時、茨城県の鹿島から来ていた人がこんなことを言った、
「天かける大鳥(飛行機)が敵国からやって来て、人々を沢山殺すような時代になったら、私たちが伝えているようなことも無意味になってしまいますなあ。
でもせめて、あなただけは覚えておいて下さい。」
太平洋戦争も末期の頃のことである。
以下は、断片的だが、ヤマトタケルにまつわる伝承を箇条で記してみる。
◦群馬県の碓氷峠の方から来た人が、「あづまはや」の呪文は、「うちの峠から言われた。海の方に向かって言われた。」と言っていた。
◦近江の方から来た人(?)が、伊吹山の神は竜または蛇だと言っていた。伊吹とは、神の息吹のこと。春が来て、神が人々を守ってやろうと目覚める。神がもう少し眠っていたい時は雪を降らす。もどし雪という。この時は祭も延ばす、と言った。この人は、ヤマトタケルは人間で、神ではないと言った。
「神の怒りに触れて殺されたのです。どれ程建々しい人でも、神の怒りには逆らえない。神の意志に従っていれば、守って下さる。」とも言っていた。
以上が、山本光子こと西山村光寿斉氏が、折にふれて思い出し、私に語ったヤマトタケルにまつわる傀儡子たちの伝承である。
断片的なものもあるが、まとまった話としては、「ほとを捧げる姫」の話と「天かける衣」の二つに分けられる。おそらく、もっと多くの物語があり、一つの壮大な叙事詞とその舞曲が伝えられていたと推察される。
この物語の外にも傀儡子たちは悲劇的な皇子や皇女の物語を多く伝えている。これらを「語り舞」と言う。その主人公たちは、いずれも不幸な生涯を送ったと語られる人々ばかりである。
菊邑検校は次のように語ったという。
「男女の恋でも、成就した話は、舞って語り伝える必要はない。それは単なる色恋にすぎない。結ばれなかった恋を舞って、死後は離れ離れにしないで下さいと神に祈る、舞って語ることによって後世の人々に『ああ、こういう恋もあったのか』と思ってもらうことが、その人々をおなぐさめすることになる。」
まさしく「語り」の真実を伝える言葉である。「語り」とは、「鎮魂」そのものであるという思想が根底にある。
「語り」の主人公の名は具体的には伝えられていない。ある尊い皇子とかやんごとない姫とかという表現しかないのである。平家の落人の公達ともまた南朝の皇子ともとれる。その方をひそかにどこかにお落しするというような振りがついている。
天皇についても、漢風謚号は一切使わず、彼ら独自の呼び方があったようである。「…のミカド」とか、「…のスメラギ」というように言っていたという。しかし、彼らが漢風謚号を知らなかったのではなく、
「とうさん(光子)たちは、仁徳と習っておいでですかね。あのミカドは大変な恐妻家でしてねえ。」
というように、わが内々のことのように、またつい昨日のことのように語ったという。
学校では、仁徳天皇は三年間税金を免除された「聖帝」と教えられた。それなのにこの人たちはその聖帝を恐妻家だという。
このように、学校で習ったことと全く違う彼らの話を聞くたびに山本光子は、これは、あの人たちだけの話で、学校で習う話とは全く別のものだと思おうとした。そして、別の記憶の部屋に閉じこめようとした、と、光寿斉氏は後年述懐している。
それゆえに、少女の頃に閉じた記憶の部屋を後年になって開いた時、傀儡子の伝えた神話は、そのままの形で世に出ることになったと考えられる。
比丘尼組と呼ばれた女性の芸能集団は、おそらく、「ほとを捧げた姫」を彼らの始祖とする一団だったのではなかったか。
彼らは、比丘尼組というその名乗りから推察するに、何代か前は遊女集団であったと考えられる。傀儡子の女が遊女であったことは、平安末期、が著した「傀儡子記」「遊女記」に詳しくその生態が記されており、明らかなことである。また中世以降の熊野比丘尼や八百比丘尼の存在を考え合わせると、信仰の宣布者であり、また売春をなりわいとしたであろうことが想像される。
しかし、そうした売春行為—彼らの言い方をもってすれば「ほとでかせぐ」こと—をなりわいとした彼らの伝承の根底に、「ほと」の呪力ヘの信仰が失われずに残されていたのである。それが彼らの誇りでもあったのだろう。
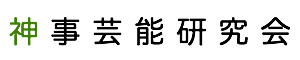
 聞書
聞書