筑紫舞聞書(七)
菊邑検校は、舞が一つ仕上がると、光子を神戸の神社で奉納させたことが何回かあった。
奉納のことは、検校より父十三の希望が強かった時もあったようである。何しろ、十三は大正天皇が崩御され、世が諒闇になったさなかに「いずれ御大典が来る。その時、わが娘を舞わさねば…」とひそかに考え、娘に地唄舞を習わせるために山村ひさ女を丸がかえしたような人であった。だから、神社に祭礼や記念行事のあるのを聞きつけては、酒を奉納し、娘を舞わせることに生き甲斐を感じていたのであった。
検校が奉納させた神社は、十三の意に反して神職のいないような山の奥の小社が多かったという。例えば次のようである。
光子の印象に鮮明に残っているのは、神鉄の有馬線に乗ってに行った時のことである。それまでの奉納の時は、店の自動車で行っていたが、今回は、電車に乗った。検校の弾く琴などは店の自動車で運んだ。
唐櫃という駅の名がめずらしかったのと、この時はじめてケイさんが舞ったので、印象深く覚えていた。
唐櫃の駅から小高い山の上に登って行くと神社があった。神主さんがいるような気配はなかった。
設営は、斉太郎がした。光子達が立っていると、社殿の前の草をすばやく刈り取り社殿の扉を空けお供え物を並べた。
この時の舞は「初瀬川」という神舞であった。ケイさんの舞姿は、この世のものとは思われぬ位見事であった。
「筑紫舞は神様にお見せするもの、見物衆は、神様のお相伴。」
と検校はよく言ったが、誠にその通り、静寂な神域に、神にのみ捧げる舞と琴の調べが流れた。
唐櫃の神社は、当時、別所諄一宮司の奉務された山王神社である。昭和六十三年六月二十四日、光寿斉氏とともに参拝した。社殿は新築されていたが、光寿斉氏の記憶にある鳥居は昔のままであった。検校達は、この鳥居の前にすわって拝礼し、して鳥居をくぐったという。
だいたいは、こんな風に、ひっそりと奉納が続けられたが、以下に述べる四社は、いずれも神戸の古社で、神職のおられた神社である。光寿斉氏からの聞き書きノートより、奉納の様子を記しておきたい。
神 社
昭和七年のはじめ、舞が一つあがった時、検校は、光子を敏馬神社へ連れて行って奉納させた。
検校は、筑紫斉太郎に、
「與市さんが、御健在ならばおことわりしておきたい。」
と言ったという。「おことわり」とは、海の神に、光子のことを御報告しておきたいというような意味であったと光寿斉氏は語った。
斉太郎が、敏馬神社へ行って来て「與市さんは、御健在です。」と報告したので、奉納することになった。検校は、この「與市さん」と心やすかったようである。
この奉納が終わるとすぐに、九州で「梅まつり」があるというのでということで、検校達は帰った。
次にもう一度、その年か、その翌年の九月のはじめ頃、敏馬神社で奉納したが、その時は、「與市さん」は、おられなかった。
昭和六十三年十一月七日、光寿斉氏と私は、敏馬神社に参拝し、宮司花木直彦氏より神社の戦前の記録等を見せていただきながら、お話を伺った。
花木宮司によれば、その「與市さん」とは、宮司の祖父・花木與市氏のことであろうという。花木與市氏は、明治五年生まれで、日清・日露の戦役に従軍され、また、能、狂言をよくされる方だったという。
花木與市氏は、昭和七年六月三十日、六十一才で亡くなっている。
山本光子が、敏馬神社に最初に舞を奉納した昭和七年のはじめには、花木與市氏は御存命であり、二回目のその年か、その翌年の九月の奉納の時には、お姿を見なかったのは、その時、既に、亡くなっておられたからである。
敏馬神社へまず一番に奉納させたのは、筑紫舞のほとんどが、海を背景にしたものであることも考えあわせ、極めて興味深いことである。
諏 訪 神 社
小学校六年生頃の十一月、光子は、諏訪山の諏訪神社で奉納した。舞殿で舞ったが、その時の舞は、筑紫琴の「四季」だったかと記憶している。筑紫琴は、検校が九州から持ってきた。この時は検校が琴、ケイが胡弓を弾いた。
参拝者などはいなかった。この時、白張姿の一人の男が印象に残った。この人は、手水舎で足を洗い、裸足で神前まで行き、自己祓をし、自分の体を両手で上からなで、その後、光子の体をすーっとなでさすった。
光子が舞っている時、この人は、舞殿の橋がかりの下に、してひかえていた。
あとで、検校に聞くと、この人は、“瀬の神のおとりつぎ”の役で、舞殿で踏む反閇を斜めに体で受け止めて神に伝える人だと言った。検校はまた、舞殿はおのころ島や淡路島などの島であるとも言った。さらに、
「瀬の神や、わたつみの神は、山にもお移ししています。海から神をお移しした山は、くずれません。人間がくずさない限りは、絶対にくずれません。」
とも言った。検校は、
「山の神と海の神は、仲良しだったんですよ。山の神は笹を持っています。海の神は塩。塩は笹の葉で取ります。仲良くしていなければ、笹がもらえない。塩がもらえない。交代する時期があったんですよ。」
とも言ったという。
山の神と、海の神は常に交流するという民族学上の重要なテーマから考えても、意味深長な言葉である。
石 屋 川 の 天 神
光子が「雷神の舞」(箏曲では「雲井の曲」)をあげた、昭和十二、三年頃の六月の初め、その日は快晴であった。光子は、検校と筑紫斉太郎と一緒にある神社に行った。この時は父が同行したが、店の者は行かず、検校の琴も運ばなかった。
石屋川の駅から川沿いの道を登って行くと神社があった。そこは、白い着物を着たお爺さんが二・三人待っていた。
光子は、父が用意した狩衣に着かえさせられ、神社に参拝した。
その時、検校が、神に向かって、大声で、
「あなたから遣わされた御子は、立派に大役を果たしました。八百万の神よ、御照覧あれ。」
と言った。すると、快晴なのに、急に稲光がして雷が鳴った。検校は、得心したように、
「あんたは、イカヅチの遣わされた御子だからね。」
と言った。父が、側で聞いていて、
「なる程なあー、そうか。」
と納得した。父は、光子が、落雷とともに、産婆も間に合わずに生まれ出た子だったので、いつも「雷さんの落とし子や」と言っていたが、検校の言うような意味もあるのかと感動した様子であった。父が、
「ガミナリやさかいに、あぶのおっせ。」
と言うのが聞こえたか聞こえずか、検校は、
「さあ、今まで習ったふりで、何でもよいから舞いなさい。」
と静かに言った。光子が、
「お琴もないのに…。」
と言うと、検校は、
「いや、舞えます。」
と言った。拝殿の前で、ひかえていた斉太郎が、ふところから石笛を出し、待っていた白衣のお爺さんはいつの間にかすりざさらを持って坐っていた。
検校は、光子に、
「最後に十三回まわり、十三回を捧げなさい。これは、一番古い神様にするもので『十三』と言います。」
と教えた。
石笛の甲高い音とすりざさらの演奏がはじまると、光子は自然と体が浮くようになって、無我の境地で舞った。今までで一番真剣に舞えたように思った。
最後に、ささらの「シャラッ」と石笛の「ピィーッ」という音で、自然と十三反閇が出来た。最後の「ピィーッ」という音で、拝礼した。
舞が終わった時、斉太郎が、検校に、
「あーあ、大盤石ですねえ。」
と言った。検校も、満足そうに、静かにうなずいた。父も、
「ほうー、えらい子授かったもんやなあ。これが男やったらええのになあー。」
とつぶやいた。
石屋川の神社とは、今の綱敷天満神社のことである。
筑紫舞の伝承では、「天満」と書いて「あまみつ」と言う。検校は、これは、天つ神のことで、菅原道真のことではないと言ったという。
筑紫舞には、天満宮系の舞がいくつかある。例えば「」。これは、天つ神の子孫が、飛び散り、天つ神として祀られるという舞である。筑紫舞では、梅は天の恵み、桜は、子孫繁栄、松は、国の栄えを表すと検校は教えた。
昭和十八年、検校は、神戸を去る時、石屋川の神社に連れて行って欲しいとたのんだ。検校は、
「光子さんをお返ししたい。」
と言った。しかし戦火が激しくて行けなかった。
神 社(海岸)
石屋川の天神で奉納した(六月)年の夏の終わりか、秋のはじめ頃、垂水の海神社の海岸で、海に立つ鳥居の方を向いて、「えの舞」を舞わされた。
砂浜に仮神殿を建てて、ござを敷いて、その上で舞った。
この舞は、え・・りの三部構成になっていて、神迎えの時は白い覆面・は笹である。
この時は、九州から三人来て石笛を吹いた。楽は、平成元年、雅楽のであったことがわかった。
舞の前に、男達は、を打ながら、祝詞のように「神迎え」の詞を奏上した。
「あまつこえ(おーと)
うみなりの
うねりにのりて
笹小舟
わが神の
来たるを待ちて
小柴たく
と来られよ
もろ待ちませり。」
というものである。この時も、十三回の反閇をした。
傀儡子芸の本質は、祓えの芸にあると私は考える。傀儡子の徒は、くぐつ芸を演ずることで、人々の穢れを身に受けることになったが、その受けた穢れを、神にゆだねる手段として、を持っていたのではなかろうか。
菊邑検校は、くぐつ舞は、「人の身をいとうて舞う翁」、神舞は「わが身をいとわねばならぬと思うて舞う翁」と教えたという。
くぐつ舞は、人の穢れを受ける舞。だから筑紫舞の翁は全身で祓えをするために、面をつけないのである。
「演ずる者が神になりきれば、面は必要ない。」
と検校は言ったという。
神舞は、検校は「人に見せるものではない」と言ったというが、穢れを神にゆだねるために、神と対するための舞であったと考えられる。だから、光子が、奉納させられた神社の多くが、神職のいないような神社だったということもうなずけるのである。
筑紫舞に、「川」という舞がある。別名「の舞」という。
この舞は、天皇より荘園に遣わされた使者が祝賀の宴で舞うという舞である。
先日、光寿斉氏と私が、湊川神社に参拝し、吉田智朗宮司よりお話をうかがった所によると、現在の神社の境内地は、昔、法隆寺の荘園であったということである。
「美奈登川」とは、あるいは、その頃の舞ではないかと考えられる。
菊邑検校の素性も傀儡子達のその後の消息もわからないままに、五十年が過ぎたが、彼らが伝えた芸とその伝承は、中世芸能史の空白を埋め、古代につなぐ何ものかを持っており、極めて貴重な文化遺産であると考えられる。そこに息づく神々は、、、と彼ら独特の呼び方で言い表され、古事記・日本書紀に登場しない数多くの神々も含め、一つの信仰的宇宙を形成していたと考えられる。
現在、神戸や、各地の神社の若い神職さん達が、神舞を伝承して下さっている。
半世紀の時をへだてて、神戸に伝えられた神事芸能が、再び神戸の地で舞われる日も近いことだろう。
らずの明石越え
現在、西山村光寿斉氏が伝承している筑紫舞は、曲数(箏曲)で言えば、二百数十曲であるが、舞の数でいうと、およそ千に及ぶと考えられる。それは、同じ曲でも、舞人の人数や、舞われる地域によって全く舞が異なるからである。そして当然、舞が表現する意味も違ってくるのである。
筑紫舞の伝承地域は、筑紫、、伊勢、出雲、尾張、、そしてと、広範囲にわたっている。
私は、昭和六十三年四月、神戸神事芸能研究会を作り、関西地方の神職や一般の人々にも呼びかけ、筑紫舞のうち、「畿内もの」の伝承にとり組んできた。
「畿内」の語は、大化改新の詔に、
「およそ畿内は、東はの横河より以来、南は紀伊のの山より以来、西は明石のより以来、北は近江ののより以来を畿内国とす。」
とある。
筑紫舞でも、「畿内」という語を使うが、筑紫舞の「畿内」は、「安芸より東、近江より西」ということになっている。
「畿内もの」といわれる舞の特長は、他の地域の舞に比べ、優雅さが重んじられる。都を含む地域だからであろうか、洗練された舞である。これを「一美一態」という。どの動作を見ても美しくなくてはならないというのが「畿内もの」には要求されるのである。
そして、もう一つの特長は、この「畿内もの」といわれる舞のほとんどが、「御印要らずの明石越え」という特権を持っていたというのである。
これは、昔、明石を越えるには、御印が必要であったが、こうした舞を持っていれば、御印なしで通してもらえるという意味である。
「御印」とは、通行手形のことである。
ここで思い起こされるのが、須磨の関のことである。「養老関市令」によれば、関所を越えるには「過書」(通行手形・通行証明書)が必要であったが、それは、船で過ぎる時も同様でそのような関は、「令義解」に、摂津と長門の二関であると記されている。この摂津関が、須磨の関のことであるとされている。
須磨の関は、海陸を兼ねた関所であった。山陽道の往還も、瀬戸内海を行く船も皆、この関を通った。その所在地については定説がない。この養老令より以前の、大化改新の詔の「赤石(明石)の櫛淵」(畿内の西限)もどこかわからないが、現在の須磨区と垂水区の境、鉢伏山の山麓が、海に落ち込んでいる辺りは、幾筋もの細い淵が海に流れこみ、櫛淵の地形を成しているので、この辺りが地形から見て納得がゆく。
たとえば、都から須磨まで陸路をとったとしても、ここから、西へ行くには、海路、明石浦を行くしかない。多井畑へまわり、山越えする道もあるが、やはり、船を使った方が速いし、安全だったと考えられる。
筑紫舞の地域は、街道ではなく、海道によって分けられている。
畿内を「安芸より東、近江より西」としたのも安芸から瀬戸内海に入り、大阪湾から、淀川を通って近江の琵琶湖につなぐ海のルートが基盤になっていると考えられる。
安芸より西、周防・長門、即ち現在の山口県は、周防灘に面しているから、海が違う。ここはもう筑紫の文化圏に入るのである。
筑紫舞の畿内ものを「御印要らずの明石越え」と称し、「須磨越え」と言わなかったのは、海道に拠っているものと考えられる。
「御印要らずの明石越え」の舞には、例えば、「須磨」「明石」「尾上の松」「末の松」などがある。いずれも「神舞」であるが、これらは皆「古神舞」と称し、遠い昔より、形をくずすことなく伝えられてきたものばかりである。
これらの舞には、「波どめ」という一つの祈願の作法が入っている。「波どめ」とは、菊邑検校は、現在でいう「波浪注意報」とか「暴風警報」のようなものであると教えたそうであるが、海路安全のため風波を鎮める祈願である。また「御印要らずの波どめ」とも言う。
おそらく、これらの舞は、海の神や、その神から見える山の神に捧げるためのものであったと考えられる。
この舞を持つ芸能者達は、船上において、この舞を舞い、おだやかな航海を神に祈ったのであろう。
そして、「御印要らずの波どめ」の祈願作法を持つ彼ら芸能者達は、これを持たない他の人々に対して職業者としての高い知識と誇りを持っていたであろう。
神に選ばれた者達のみが持つ特権意識が、筑紫舞すべてに感じられるのである。
これらの舞は、すべて伝承が終わった。畿内ものの伝承に取り組んで二十余年。筑紫舞のなかでも数も多く、また高度に洗練された技が要求される畿内ものの伝承は、前途はろけきものがある。
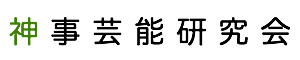
 聞書
聞書